
���@�B�̃G���W���́A���i�ڂɂ�����̂Ƃ̓P�^�Ⴂ�̑傫���ƃp���[������Ă��܂��B�܂��A���@�B�̎d����ʂ��đ����̐l�X�̐������x���邱�Ƃ��ł��܂��B���̃G���W�����J���ł���̂́A�A�E�ɂ������čł����͂���I�����ł����B���Ќ��8�P�������Č��C���A��b�I�ȋZ�p�E�m�����K�����܂����B�U��Ԃ�ƁA���̊��Ԃɓ����Ƃ̂Ȃ��肪�ł������Ƃ��傫�Ȏ��n�ł����B�d����̋^��⑼����̏��C���˂Ȃ�����E���L�������W�ł��B

�S�����Ă���̂́A�u�^�[�{�`���[�W���v�̐v�J���ł��B�r�o�K�X�̃G�l���M�[�𗘗p���āA��葽���̋�C���G���W���֑��荞�ޕ��i�ŁA�o�͂�R����łȂ����Ή��̎��_������d�v�ȃf�o�C�X�ł��B���̃`�[�����R�}�c�̌��@�B�̃^�[�{�`���[�W���̊J�����ꌳ�I�ɒS���Ă��܂��B����3�N�قǑO�A���ɓ����������݂��~�����ƍl���A��]���o���ăG���W���J���S������v�f�J���S���̃`�[���ֈٓ����܂����B���݂͎�����G���W�������̊J�����i�s���ł��B�u�v�f�J���v�́A�G���W���S�̂ցA�ԑ̂ւƑ��������H���̐擪�ɂ��镔��ł�����܂��B�x�ꂽ��S�̂Ɋւ��Ƃ����ӔC�����ЂƂ̃��`�x�[�V�����ɂȂ��Ă��܂��B

�^�[�{�`���[�W���͑傫�����̂�50�`60kg�ɂ��Ȃ�܂����A1mm�ɂ������Ȃ����ׂȈႢ�ł����\���傫���ς��܂��B�����炱����������̑O�ɁA�ł�����萳�m�ɐ��\����荞�ނ��Ƃ��d�v�ł��B���̃`�[���ł͈ȑO��������͂����p���Ă��܂������AMBD�iModel Based Development�j���i�̗�����Ă���ɐ��x�����߂�ׂ��A�V����CAE�iComputerAided Engineering�j�����p���p���I�ɉ��P���s���Ă��܂��B�u��͐��x����v�̂悤�ȃe�[�}�́A�J���Ɩ��Ƃ͕ʎ��Ńv���W�F�N�g�`�[���𗧂��グ�āA��Ђ̃o�b�N�A�b�v�̉��Ō�����i�߂Ă��܂��B�e�[�}�͏�ɕ�������A�v���W�F�N�g�̔����͎����I�ł��BIPA�ɂ́A���Ƃ��Ɓu�����B�͒�ēI�ł���ׂ����v�ƍl����Е�������悤�Ɋ����܂��B����l���Ē�Ă���p�����A�������̃e�[�}��\���I�ɐ��ݏo���A�Z�p�̐i���̌����͂ƂȂ��Ă��܂��B

�d�������Ă��ėǂ������Ɗ�����̂́A�J���Ɍg������G���W�����H����ɕ���ł��鎞�ł��B�܂��A�C���h�l�V�A�ւ̏o�����ɁA�ԗ��Ƃ��Ċ������H����ɂ����������ł���l�q�����߂Ėڂ̓�����ɂ��A���߂Ċ������܂����B�����āA�玙�x�Ɏ擾�ɉ��̃n�[�h�����Ȃ����Ƃ��AIPA�̗ǂ��Ƃ���ł��B���͎q�������܂ꂽ����3�P���قLj玙�x�ɂ����܂����B�q���͖����ǂ�ǂ�����̂ŁA�������ŕω������Ă���ꂽ�̂́A���e�Ƃ��Ă��������̂Ȃ����Ԃł����B�Ɩ��ւ̕��A���X���[�Y�ŁA���̉�Ђɓ����ėǂ������Ƒf���Ɏv���Ă��܂��B

���͓��Г�������V�^�G���W���̊J���Ɋւ���Ă��܂����B���̃G���W���́A�ϋv�����ێ����A�R������P���邱�Ƃ�ڕW�ɊJ������Ă��������ヂ�f���ł��B��������ʂ���Z�p���̎��W�E�������s���A�v���W�F�N�g�`�[���ŃV�~�����[�V�����A����A�����A���P���d�˂Ă��܂����B���݂́A��^�̃x�[�X�G���W�����z�C�[�����[�_�[��u���h�[�U�[�ȂǑ��l�Ȏԑ̂ɓ��ڂ��邽�߂̐v�Ɩ���S�����Ă���A�ʎY���̖ڏ����������Ƃ���ł��B
�G���W���J���S���́A�v���W�F�N�g�����[�h���i�����Ǘ���������ł��B���m���܂��A�ԑ̊J�����哙�����ʂƃR�~���j�P�[�V������}��v���W�F�N�g��i�߂܂��B�����g�́A����5�N�ڂ̃W���u���[�e�[�V�����ŃR�}�c�̎ԑ̊J������ł̎d�����o�����A�V���Ȏ��_�Ɛl����IPA�ɖ߂邱�Ƃ��ł��܂����B�傫�ȃv���W�F�N�g�ŁA�G���W���ɂ��ԑ̂ɂ����ʂ����u�ʖ�v�Ƃ��Ă̖������ł��邱�Ƃɑ傫�Ȃ�肪���������Ă��܂��B
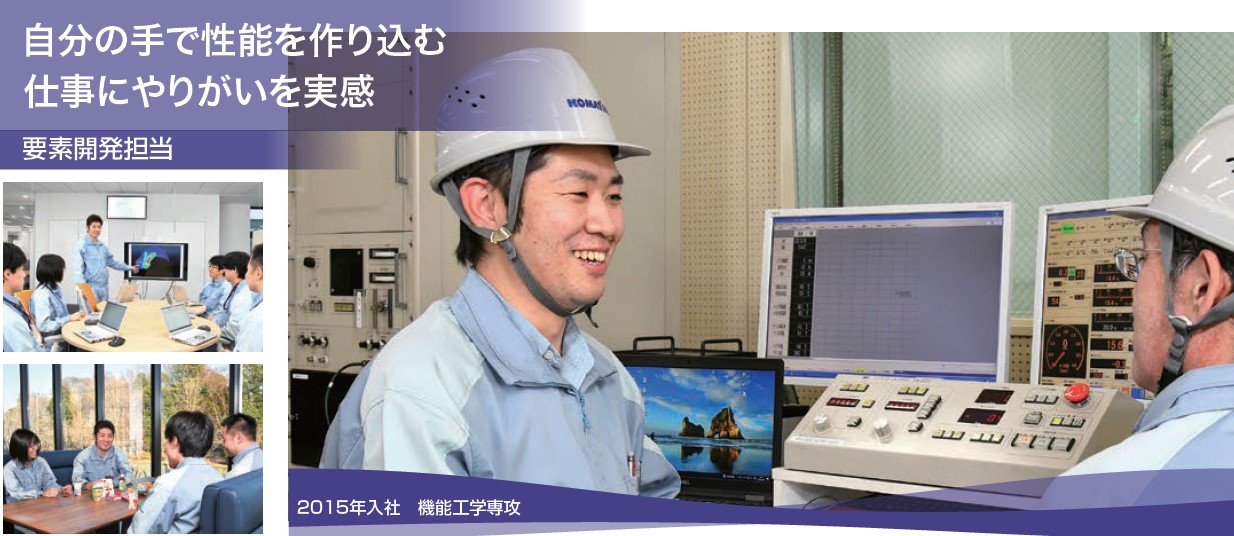
������������̂́A�G���W���̓��]�ł���R���g���[���J���̐�啔���ł��B�@�R���g���[���̃n�[�h�E�F�A/�\�t�g�E�F�A���J������`�[���ƁA�A��̓I�ɐ��l���������v�����\�ɍœK������`�[���ɕ�����Ă���A���͇A�̐��\�`�[���ɏ������Ă��܂��B���\�Ɋւ��C���W�F�N�^�[��^�[�{�Ȃǂ̎d�l�I����s���Ă��܂��B�������N�g����Ă���������G���W���͔R�Čn����v�������������f���̂��߁A���Ɍ����Ȍ������d�˂Ă��܂����B
���@�B�͐��烁�[�g���̍��n�⊦����ł������ԗ��ł��B��ɃA�N�Z���S�J�ʼnғ������A�y���ɑ̓����肷��悤�Ȏg����������\��������܂��B�V�r�A�ȏł����ɐ��\�������邩�A�������鐫�\�̃o�����X�������ɍœK�����邩�����߁A�`�[���Ő��\����荞��ł�����肪���̂���d���ł��B���s����̖��ɑ_�����ʂ�̓��������Ă��ꂽ���͒B����������܂����A���ゾ���łȂ��A���ɂ͎��ۂɃG���W�����Č������Ă����̂������ɍ����Ă���A�d���̃��`�x�[�V�����A�b�v�ɂȂ����Ă���Ǝv���܂��B�N��E�o���Ɋւ�炸�ӌ������킹��Е������S�n���ǂ��ł��B

�G���W���J���S���́A�R�}�c�̌��@�B�ɍڂ���G���W�����J���E��������ɂ�����A�S�̂��܂Ƃ߂郊�[�_�[�̂悤�ȑ��݂ł��B���̂��ߋƖ��Ŋւ�镔��́AIPA���݂̂łȂ��A�R�}�c�̎ԑ̊J������A�H��̐��Y����A�i���ۏؕ��哙�Ɣ��ɕ��L���ł��B�G���W���J���́A�傫���x�[�X�G���W���J���ƁA�ԑ̂̎d�l�ɍ��킹�ĊJ������i�K�Ƃɕ�����܂��B���͓��Ќシ���Ƀx�[�X�G���W���̊J�������A���̌�T�N�قǖ����V���x���̊J���ɂ��g���܂����B���݂�20t�N���X�����V���x���ɍڂ��鏬�^�G���W���A���ɁA���B�����̐V�r�o�K�X�K���ɑΉ�����J����S�����Ă��܂��B

���i�̋Ɩ��̒��ł�肪����������_�́A�����̐v�����m�ɂȂ�A�@�\�������ł��B����œ���Ɗ�����_�Ƃ��āA���@�B�ɂ́A������ߍ��Ȋ��ł����Ȃ������M���������߂��܂��B���̖ڕW��B�����邽�߂ɂ��A�J���̒��ŗl�X�Ȏ������s���Ă����܂����A���ׂđz��ʂ�ɍs���킯�ł͂���܂���B�ނ���z��O�̖��������ĉ������邱�Ƃ��d�v���ƁA���͎v���܂��B���̂悤�ȋ�J�̖��ɊJ�������G���W���̗ʎY���n�܂鎞�A��ԒB�����������܂��B

���X���͑�w�ŃG���W���̌��������Ă��܂������A���ۂ̎d���͗\�z�ȏ�ɕ��L�������Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��B�������A��w�Ŋw�͊w�̒m���Ȃǂ͎d���ł悭���p���Ă���A���܂��ɋ��ȏ�����������o���@�����A�����ƕ����Ă����悩�����Ǝv�����Ƃ�����܂��B����ŁA�����Ŏg���m����Z�p�͐�y�ɕ�������A�Г��ɂ��鎑�����Q�l�ɂ��Ȃ���w��ł��܂����B�܂��A�O��̂Ȃ��V���������K�v�Ȏ��Ȃǂ́A�����ʼn����𗧂āA�`�[���ŋ��L������A��啔���ɑ��k�����肵�Ȃ���i�߂邱�ƂɂȂ�܂��B�������Ƃ��ɑ��k�ł���l�������̂͐S�����̂ŁA�l�Ƃ̂Ȃ������邱�Ƃ��ƂĂ��厖�ł��B

���@�B�̃G���W���́A��p�ԂȂǂƂ̓G���W���̎g�������S���Ⴂ�܂��B�A�N�Z���S�J��1�����A���N���ғ��������A���o������������A���������肷��ߍ��Ȋ��ł��g���܂��B�܂��A�R���g�p�ʂ��ԂƂ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǑ����̂ŁA���q�l�͔R��ɂ��V�r�A�ɂȂ�܂��B���̂悤�Ȏs��ŁA�R�}�c�̌��@�B�̃G���W���͕]�����������ƂɌւ�������܂��B�ߔN�͒E�Y�f�̊ϓ_����A���@�B�ł��d�������i��ł��܂����A������x�G���W���̃j�[�Y�͎c��Ƃ��l�����܂��B����ŒE�Y�f��r�o�K�X�K���͐i�ނ̂ŁA�Z�p�i���͂���ɋ��߂���ł��傤�B�J���̃n�[�h���͍����ł����A�����ɂ�肪���ł�����܂��B

���BCAE�iComputer Aided Engineering�j�`�[���́A���G�ȃV�~�����[�V������͂ɂ��J���T�|�[�g�ƁAMBD�iModelBased Development�j�Ȃǂ����p���������I�ȊJ�����������邽�߂̋Z�p�m�����s���Ă��܂��B�Z�p�̐i���Ƌ��ɂ��L�͈͂ɂȂ����o�[�`���������ŁA�J���̃t�����g���[�f�B���O���������J���X�s�[�h�E�R�X�g�����������邱�Ƃ��_���ł��B�����͂����߂�Ӗ��ł��d�v�ȃZ�N�V�����ŁA�l���K�͂��N�X�g�債�Ă��܂��B
��͂ł͂����Ɍ������|�C���g�Ƀt�H�[�J�X���Č��ʂ��o�����A���������̐��x�邽�߂ɂ͂ǂ�ȃC���v�b�g���K���A���ꂱ�ꉼ���𗧂ĂăA�v���[�`���܂��B�����g�́A������G���W���̃V�����_�u���b�N��V�����_�w�b�h�̎��O�]����S�����܂����B�������\�������ʂ�Ɍ��ʂ�������̂͋C�����̂����u�Ԃł���A�e��啔��ƍL���ւ��邱�Ƃɂ��y�����������Ă��܂��B�R�}�c�͊C�O�ł̃V�F�A�������AIPA�̓A�����J�̃J�~���Y�ƃR�}�c�̍��ى�Ђ̂��߁A�C�O�Ƃ̂��Ƃ肪���Ȃ�����܂���B�����A�����J�Z�p�����ɍs���܂������A�O���[�o���ȑ��ʂ����͂̂ЂƂł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�R�N�ԁA�V�J�S�̃R�}�c�A�����J�iKAC�j�ɒ��݂��Ă��܂����B�G���W���̃v���Ƃ��đ㗝�X�̖⍇���ɉ����A�C���̑���╔�i���������ł��B���n�ɔ��Ō��������ɓ����邱�Ƃ�����܂����BIPA�ɓ��Ђ��������͗v�f�J���S���ł������A���ЂT�N�ڂ̖ʒk�ŗ��w���x�ɋ���������Ƙb�������Ƃ��n�ĂɂȂ������Ǝv���܂��B�Őf���ꂽ���͋����܂������A��Ԏ��ň����܂����B
�A�����J�̕��i�̒��Ō��錚�@�B�́A�ЂƖ��Ⴄ��ۂł��B�����ł��悭�������A���E���ɐ��i���͂��Ă���A�����͐�����Ђɓ������Ɗ����܂����B�R���i�ЂŁA���n�̕�����d���̐i�ߕ��Ɋ����܂Ŏ��Ԃ�������܂������A���ԂɁu���O�͂悭����Ă���v�ƌ����Ă��炦�����͊����������ł��B�u�ǂ��ɍs���Ă������͂���v�Ƃ������M�����܂����B�܂��A���Ƀ��[�U�[�ɉ�A���|�[�g����͌����Ă��Ȃ��z���ɐG��āA�g�����̎��_�⌻�n�T�|�[�g�̓w�͂��m��܂����B���̐l�B�̂��߂Ɏd�������Ă���Ƃ����������N���܂����B���{�ɖ߂��������A�J���������m�̐�ɂ��邨�q�l���ӎ����Ă��܂��B���ꂩ������q�l�ɁuI love it�v�ƌ����Ă��炦��G���W���𐢂Ɏc�������ł��B
